文芸部IWATE
第38回全国高校文芸コンクール
岩手県勢入賞作品紹介
昨年行われた第38回全国高校文芸コンクールは7部門に22,957点の応募があり、岩手は6部門で31作品が入賞。スタンダードでは今回入賞した全作品を紹介します。
▶︎ 小説部門(6作品)
▶︎ 随筆部門(1作品)
▶︎ 詩部門(6作品)
▶︎ 短歌部門(6作品)
▶︎ 俳句部門(6作品)
▶︎ 文芸部誌部門(6作品)
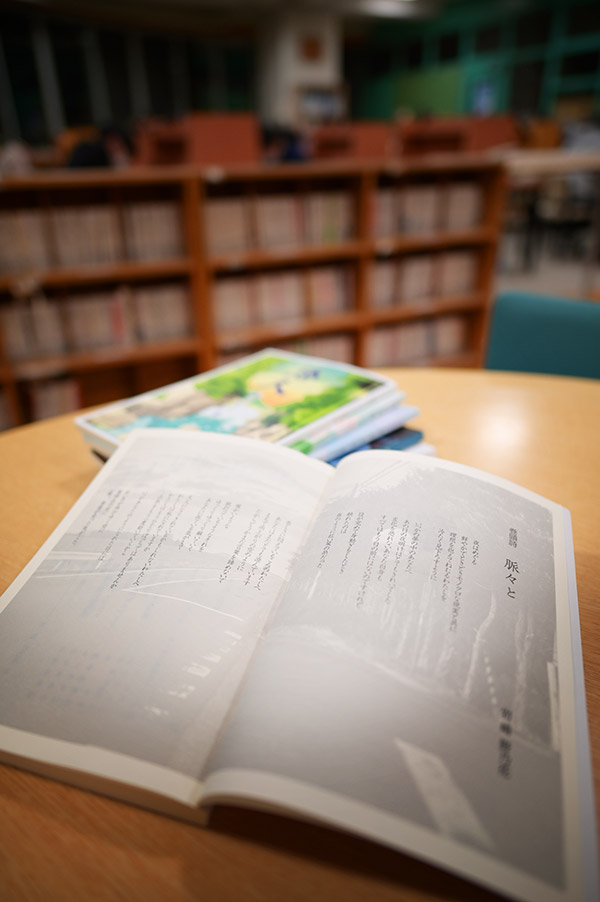
小説部門
優秀賞
僕らは集まり文字となる
盛岡第四高校1年 高橋舞
この小説のテーマは、他社理解と人の温かさについてです。今まで苦手だった人の新たな一面を知る。目に障がいのある人などの、自分は想像するしかできない相手への理解。兄弟間の距離感。それらの私が描きたい日常の気付きや小さい優しさたちを詰め込みました。ぜひ読んで、誰かの心に温かく残ってほしいと思います。

放課後の推し姫
盛岡第二高校3年 高宮花那
この作品は可愛いものが好きな男子高校生浜村渚が、渚を「推し」として崇拝する女の子、高野風花とであったことで過去のトラウマから解放されていくストーリーです。「推し」という多くの人にとって身近な存在を題材にしたので、親近感を持って読んでいただけるのではないかと思っています。

願いごと
盛岡第三高校2年 小野光璃
同じ名前のクラスメイトがいることで比べられる優太。そのことを複雑に思いながら過ごしていると、ある日、公民館でユメカという少女と出会う。ユメカと交流するうちに優太の心境にも変化が……。
読んでいるうちに肩の力が抜けるような、柔らかい物語を目指しました。

優良賞
Pan-Breadism(汎パン主義)
盛岡第四高校2年 小山文遥
パンにかける熱意、そして愛を込めた食レポ。ふんだんに使われた比喩。これらの三重奏が織りなす物語。それはまるで鬼に金棒である。ちなみに食パンはレンチンするとモチモチになって美味しい。

入選
アフターストーリー
花巻北高校1年 及川讃香
この作品はAIが発展していくにつれ、私たちの音楽の形はどうなっていくのか、そしてそのAIの発展を受けて人々はどんな行動をするのかというところをポイントとしています。人間とAIの線引きをテーマにおいて、AIの可能性とそれで生じる私たちの文化の危機を想像しながら読んでいただきたいと思います。

11月の極夜
盛岡第四高校3年 佐藤恭介
私がこの作品に込めたメッセージは自分を認めてくれる大切さです。
主人公はナルコレプシーであるがゆえにほかの人から大学受験の合格を認められず、その生活の不便さから少し卑屈な性格でしたが、高校からの友人の言葉で自身の陰を少し無くせました。誰かを認めることでほかの人の苦悩を無くせたらいいです。

随筆部門
優秀賞
隣、いいですか?
盛岡第三高校2年 小野光璃
「隣、いいですか?」この言葉は、私が春にかけられたものです。私の隣には女性が座り、車内は一気に賑やかになります。バスを単なる移動手段だと思っていた私にとって、それはとてもびっくりする体験でした。
そのときの状況や、私の思ったこと、感じたことをまとめてみました。
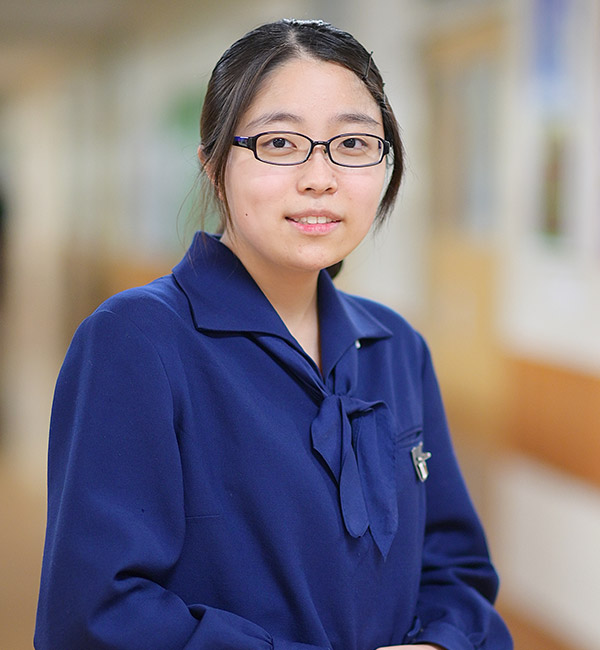
詩部門
優秀賞
月に揺蕩う
一関第一高校2年 千葉真桜
初めて作った詩であること、性別や体の問題に触れることをテーマにしたこともあり、挑戦する作品になりました。見どころとしては、性や体に関わる内容を盛り込むにあたって、色彩や比喩を多用して言葉を表現したところです。それによって、ただ生々しいだけではなく神秘性を秘めた不思議な雰囲気の作品になりました。

数学の詩
盛岡第三高校3年 水上桃果
定義に当てはまらないものはすべて成り立たない。そんな常識に縛られず、自分の素直な気持ちを大切にしてほしい。そんな想いを込めた詩です。『xページy行目』などの表現で、数学の堅い印象を持たせつつ、『片想い』のテーマの中に私自身の気持ちも織り交ぜることで、感情の自由さを表現しました。誰かの心に響けば幸いです。

優良賞
春嵐探し
盛岡第三高校3年 岩崎野乃花
18歳になる前に音楽を聴いていてふと考えたことをそのまま書き留めたものがきっかけでできた詩です。平仮名での表記を織り交ぜながら書くことで、独白の中に私自身の本心が混じっていることを表現しました。この詩を読み終えたとき、読んでくださった方の心に少しでも余韻を残すことができれば幸いです。

~だとか
盛岡第四高校3年 髙嶋こはく
後悔が善だ悪だと嘆かず、どんな過去も丸ごと愛してあげたい。という思いから作った詩です。言語化できなかった心も闇に葬りたい行動や衝突も、一般的に美とされる経験と同じく必死に生きた証拠だと思います。未来はわからないからこそ、自分なりに今を生きることが、一つでも多くの救いになってほしいという願いを散りばめたつもりです。

入選
Mother
水沢高校1年 佐藤明彩
この詩の見どころは最後の「臍の緒」という表現です。終わりのない恐ろしい宇宙をまるで恋をしているように見つめる私たちがいる。それって宇宙という母を1日でいいから見てみたいのかもしれないと思いました。そう考えたら宇宙服とステーションを繋ぐあの命綱が私には臍の緒に見えたんです。

コンデクターの0.1秒
盛岡第二高校3年 佐々木椿
指揮者がタクトを振り上げ、最初に一振りする瞬間に焦点をあてた詩です。その一瞬にさまざまな物語がたくさん詰まっていると感じました。たくさん練習してやっと本番を迎え、始まった瞬間にこれまでの苦悩がすべてはじけ飛ぶような感情と臨場感を感じていただければと思います。

短歌部門
優秀賞
手荷物は…
盛岡第三高等学校1年 田島颯大
この作品の見所は、二句切れで前半に自分の感情、後半に情景を置いた点です。この作品は自分が実際に旅をした時に感じた、日常からの解放を表現しました。そのため強い感情である「手荷物は何もいらない」を最初に置き後半にそう感じた理由として自由の象徴かつ実際に旅の途中で見た羚羊を置きインパクトを与えています。

おだやかに…
宮古高校定時制4年 大井彰浩
何気なく通学路を歩いていると、ふっと思う瞬間がときどきあります。いつかまた大地震が起こり、今見えている景色が破壊される時が来るのだろうな、と。この気持ちを率直に表現したのが、この短歌です。上の句では震災前の風景を、下の句で震災直後の風景を示し、短歌全体の対比を意識しています。

優良賞
田に刺さる…
花巻北高校3年 佐藤颯太
大事にしたのは、自分が日ごろ感じている思いを率直に短歌に表現したところです。通学路の田んぼに無造作に置かれただけの誰の目にも止まっていない選挙の看板から感じる私たちの社会に対する冷めた視線と、諸問題が未解決のまま多く存在する一方で自分の生活だけを考えてしまう自身をふと考え、口だけでなく本当の平和が来てほしいという願いを込めました。

「豪遊」と…
盛岡第四高校1年 谷藤凜香
「豪遊」という少し小難しい言葉を嬉々として使いながら、安い菓子を買う子どもの無邪気で可愛らしい様子を思い浮かべて詠んだ作品です。子どもの声や表情を思わず想像し微笑ましくなる、そんな短歌を目指しました。和やかな空気感を味わってほしい一首です。

朝刊と…
盛岡第三高校2年 佐藤麻尋
寡黙な「父」が寝息を立てている「母」に微笑むというギャップによる面白さを感じられると同時に、心の中では「父」が「母」を愛おしく思っているのだろうと想像され、ほっこりした気持ちになれるのがこの歌の魅力です。

入選
鴨たちの…
盛岡第四高校3年 深澤海都
その日はテスト期間だったかで、少し早い時間に下校しました。いつも一緒に帰る友達は用事があったようで一人のほほんと自転車を漕いでいたところです。河川敷のあたりでは市中から集められた雪を機械がえっこら均しており、その足元のぬかるみにはぽつぽつと水たまりがあります。陽に目を細め、鴨たちもまたのほほんとしておりました。

俳句部門
優秀賞
獣道…
一関第二高校3年 菅野汐那
母と喧嘩してプチ家出をした際の、地元藤沢町の景色を詠み込んだ一句です。「廃屋」の不穏さから、ぱっと明るい空気に切り替わる「芝桜」の美しさを意識して詠みました。審査員の先生から「寂れから生命力への転換が鮮烈」であると褒めていただきました。全国コンクール俳句部門で2年連続入賞を果たすことが出来てとても嬉しく思っています。

優良賞
両の手で…
盛岡第三高校3年 水上桃果
この俳句は、啄木の短歌について研究する、という文芸部誌の企画を通して完成した俳句です。私のお気に入りのフレーズは『両の手で』です。盛岡ゆかりの歌人・啄木が残した数々の歌から言葉を拾い集めて研究し、私たちの作品に活かす。そんな盛岡を舞台とした時代の繋がりを感じられるような俳句にしました。

入選
大風に…
盛岡第二高校2年 淵澤春風
子どものころ雪の上で凧あげをしていたら、風が強く吹いて凧が遠くに飛ばされてしまった思い出があり、そのときの光景を詠んだ俳句です。凧に描かれていた絵柄が歌舞伎役者のようだったので、風に舞う凧を歌舞の舞に例え表現しました。

蝌蚪の群…
水沢高校2年 菊地るな
無秩序な交差点のように色々な方向に進むたくさんのおたまじゃくしを見て詠んだ句です。漢字を用いたことでおたまじゃくしの多さや色々な方向へ泳ぐ様子を表現できたと思います。また小川や池、沼などの自然豊かなところにいるおたまじゃくしと人工物である交差点を渡る人々という、似ていながらも対比になっているところがこの句の見どころです。

傷つけた…
盛岡第三高校3年 金優希
この歌では、主人公は喧嘩をした後で、友人や家族といった、大切な人を傷つけてしまったことを後悔する様子を詠んでいます。アイスクリームを食べた時の、体の中がじんわり冷えていく感覚と、主人公の中で広がっていく胸の痛みや辛さを重ねました。

月涼し…
久慈高校長内校1年 金澤ほのか
この俳句は、「恋」をテーマにして作りました。初恋の内緒話をするときの気持ちと、夏の季語である「月涼し」がもつ美しさや爽やかさを取り合わせて作ったので、この句の意味や場面を思い浮かべて皆さんに読んでいただけたらと思います。

文芸部誌部門
最優秀文部科学大臣賞
黎(れい)第23号
盛岡第三高校
優秀賞
志高文芸 第57号
盛岡第四高校
奨励賞
花北文学 66
花巻北高校
悠久 第21号
一関第一高校
煌 第20号
水沢高校
はなぶさ 第47号
盛岡第二高校
